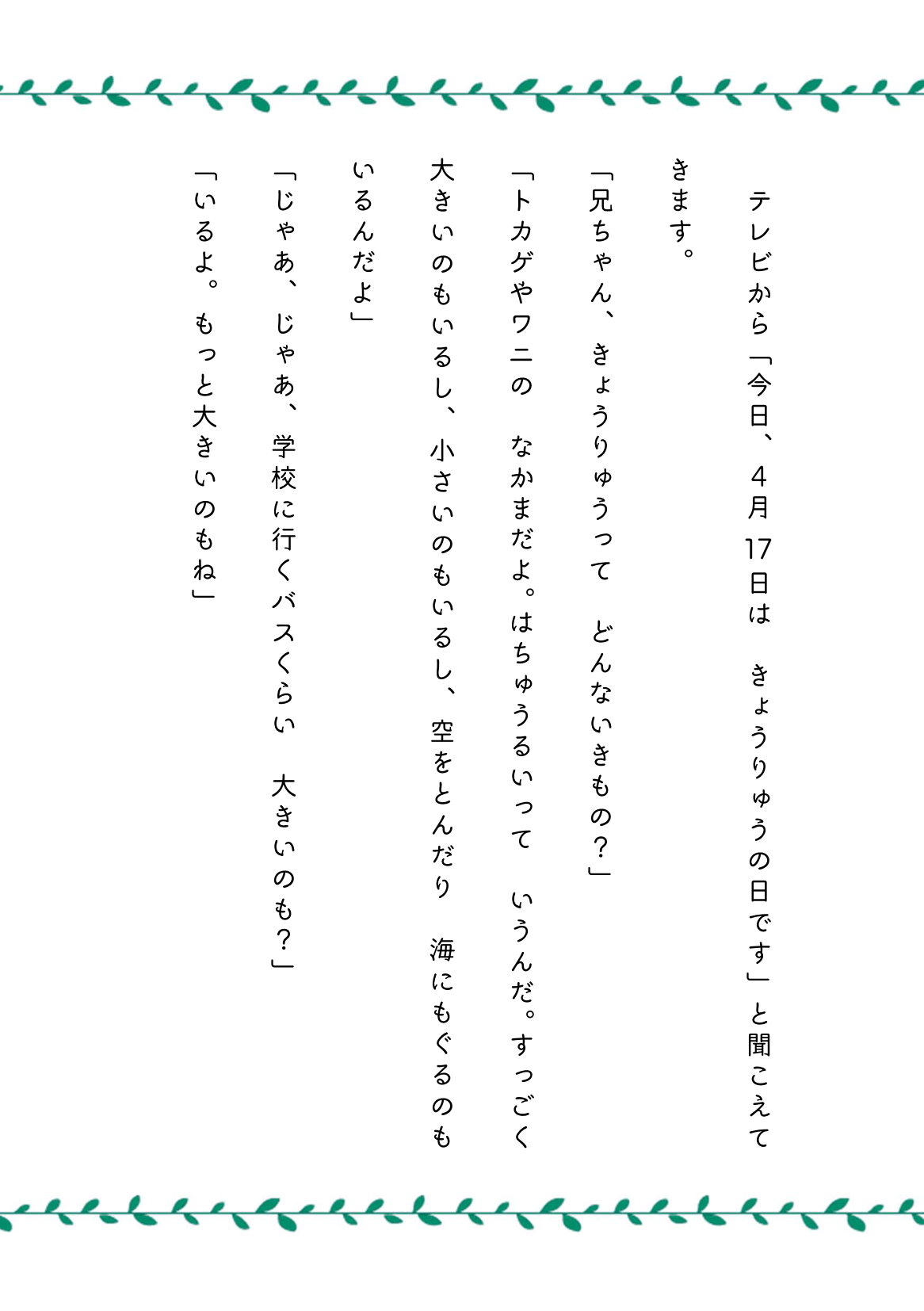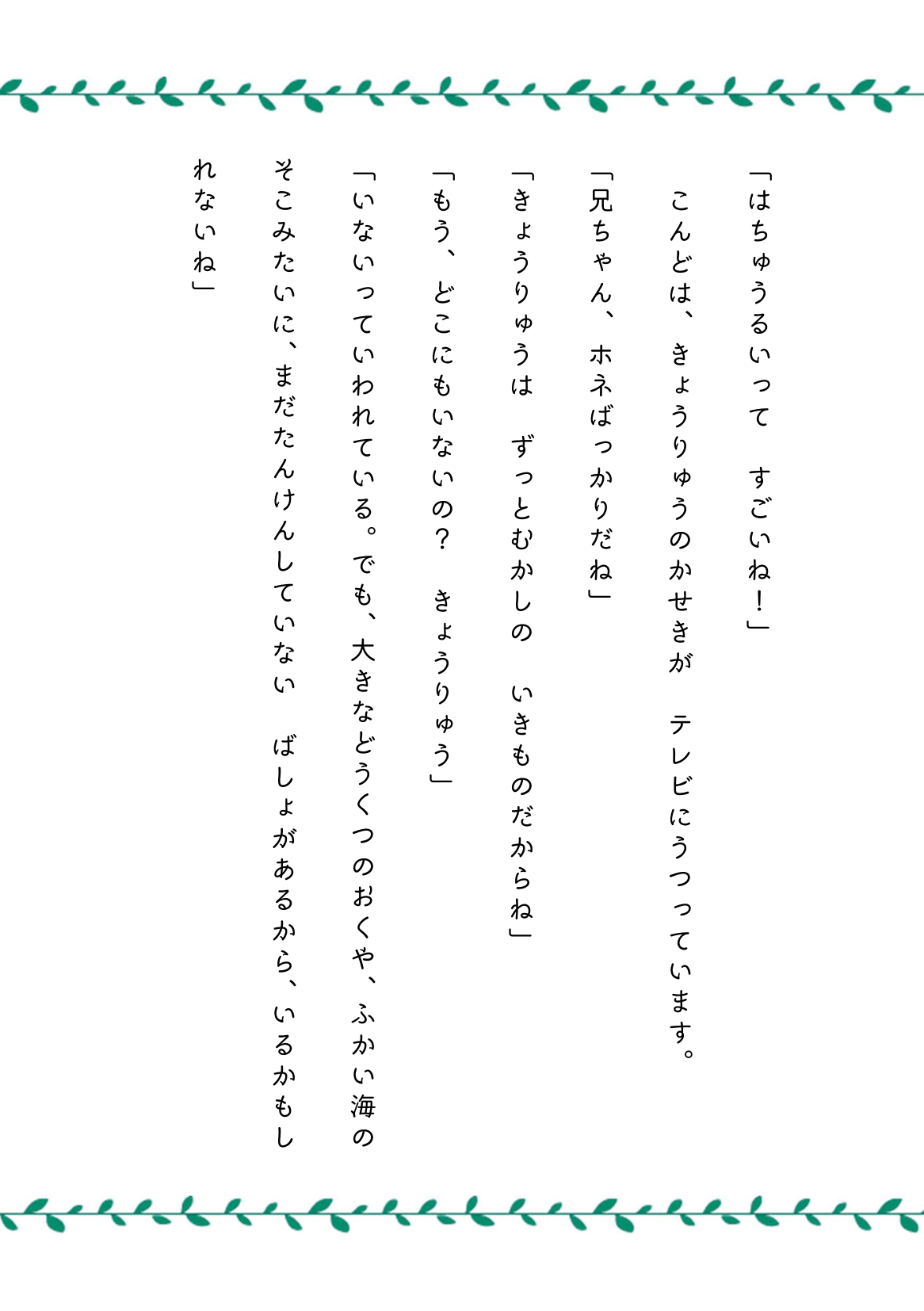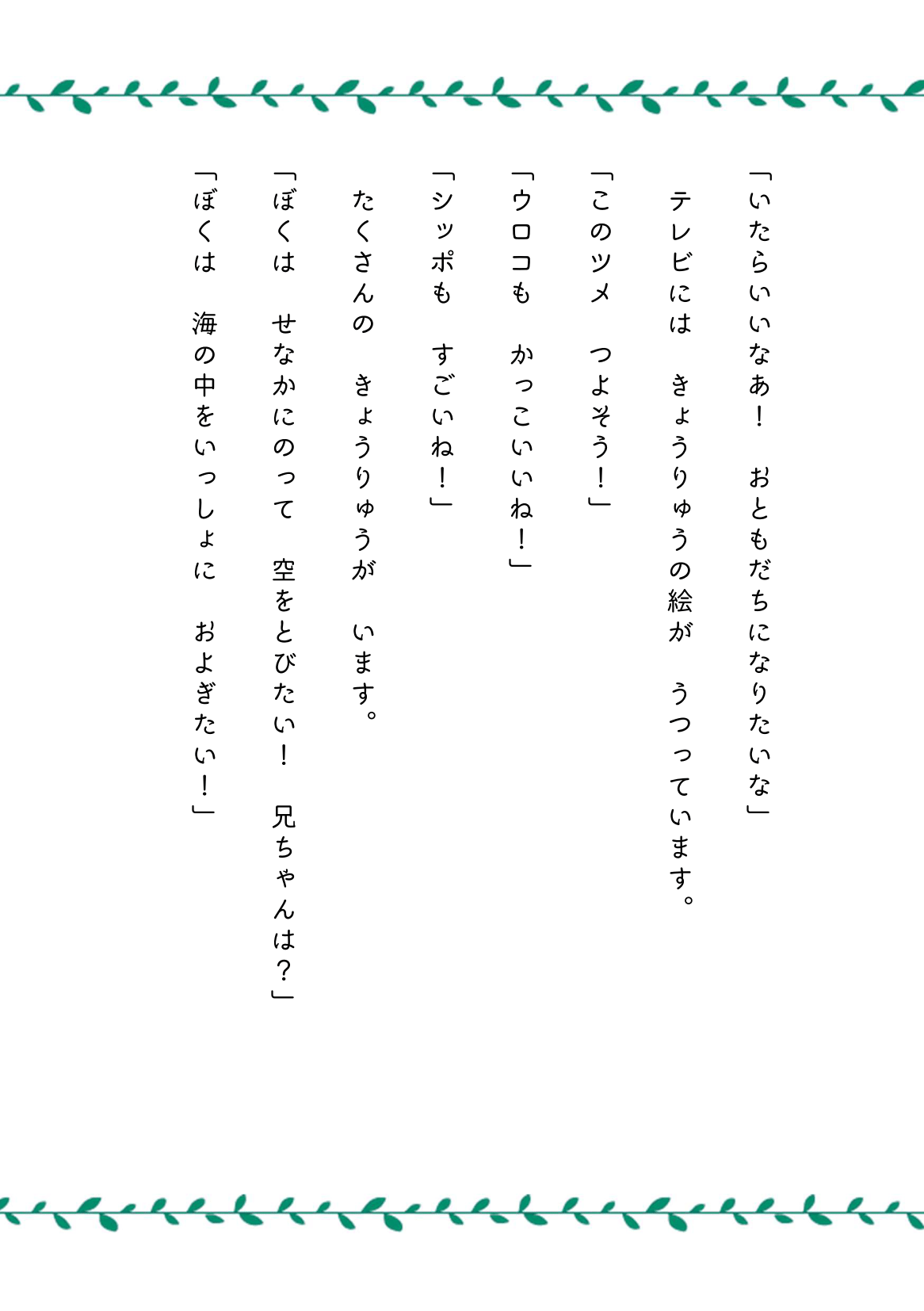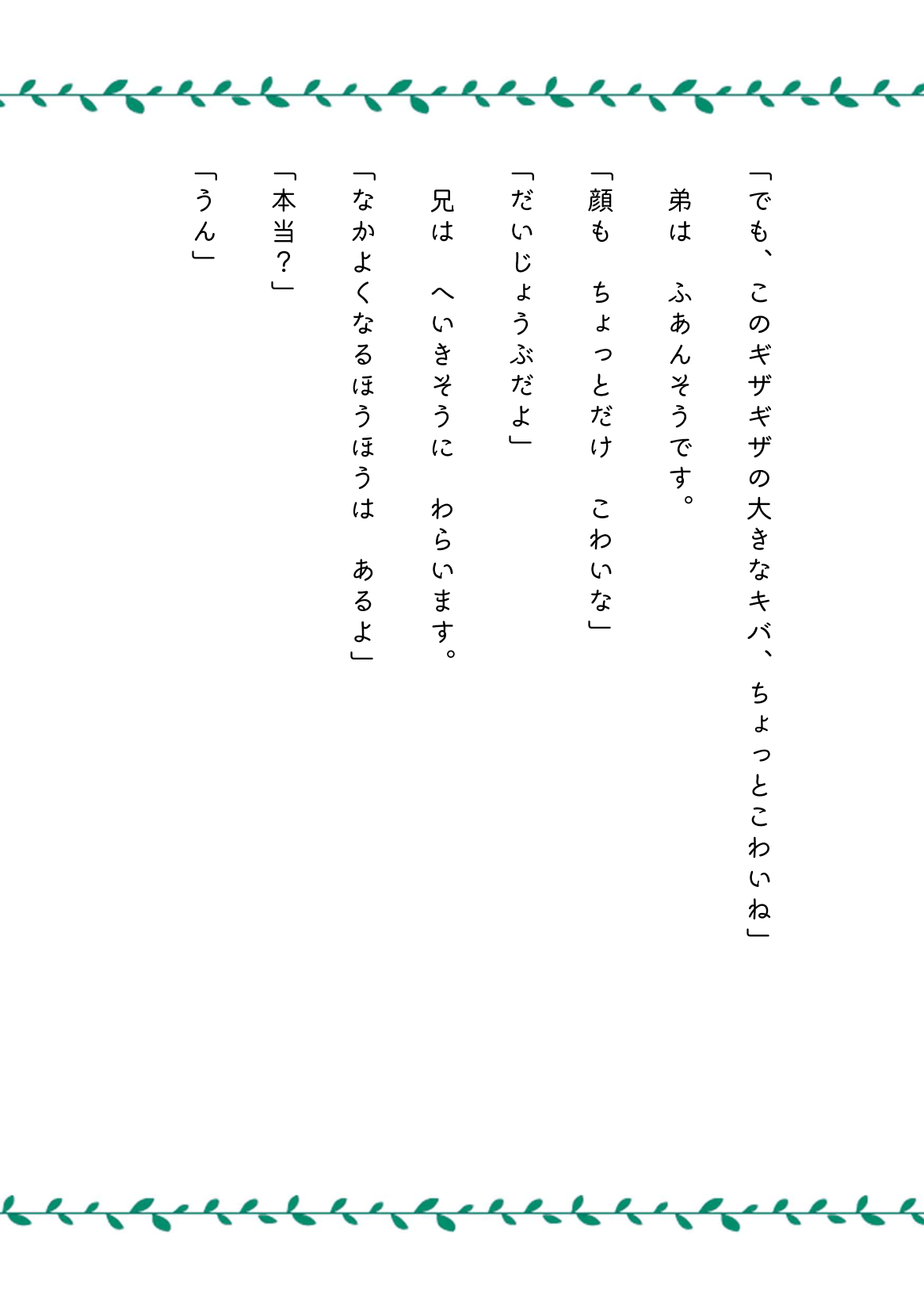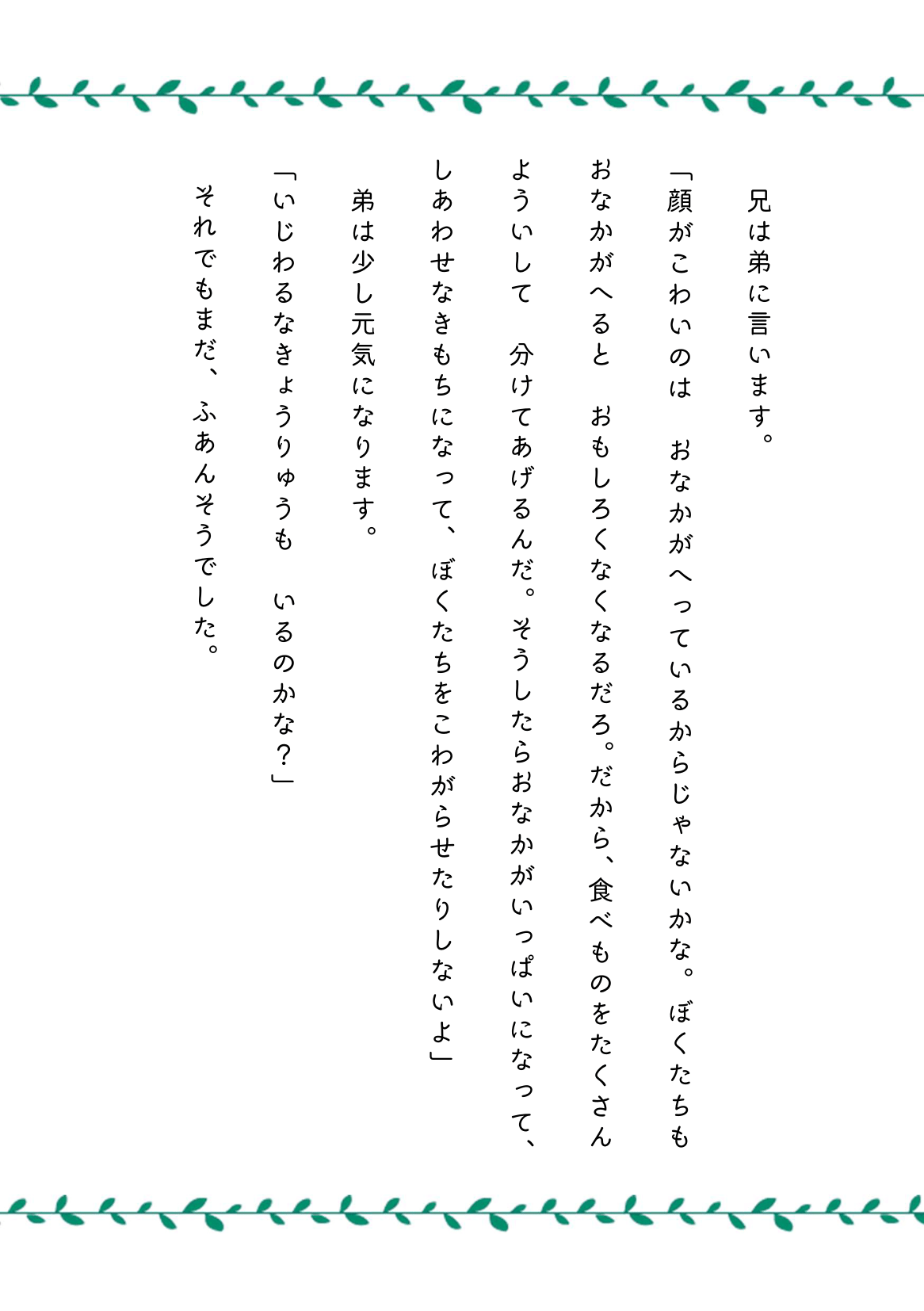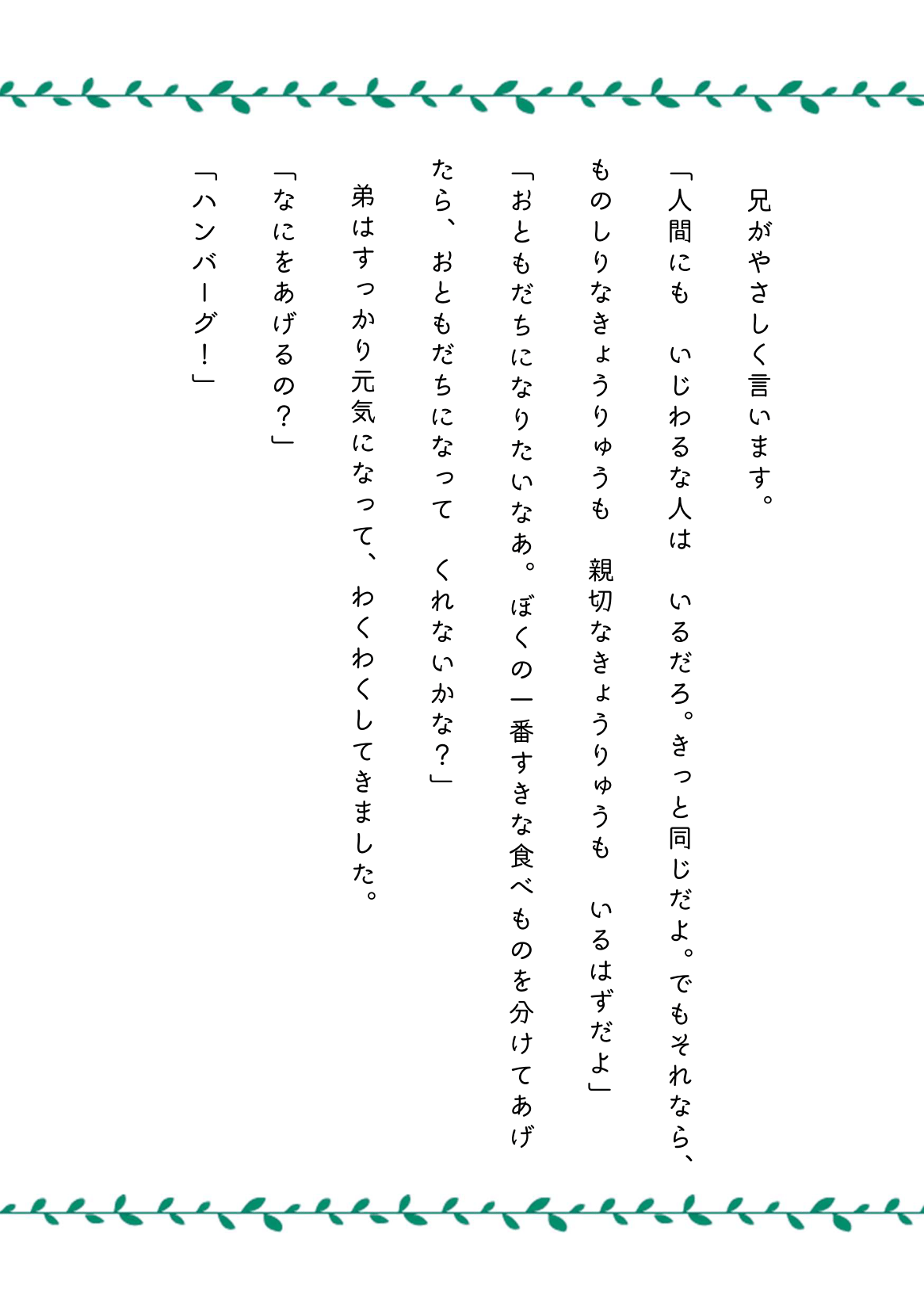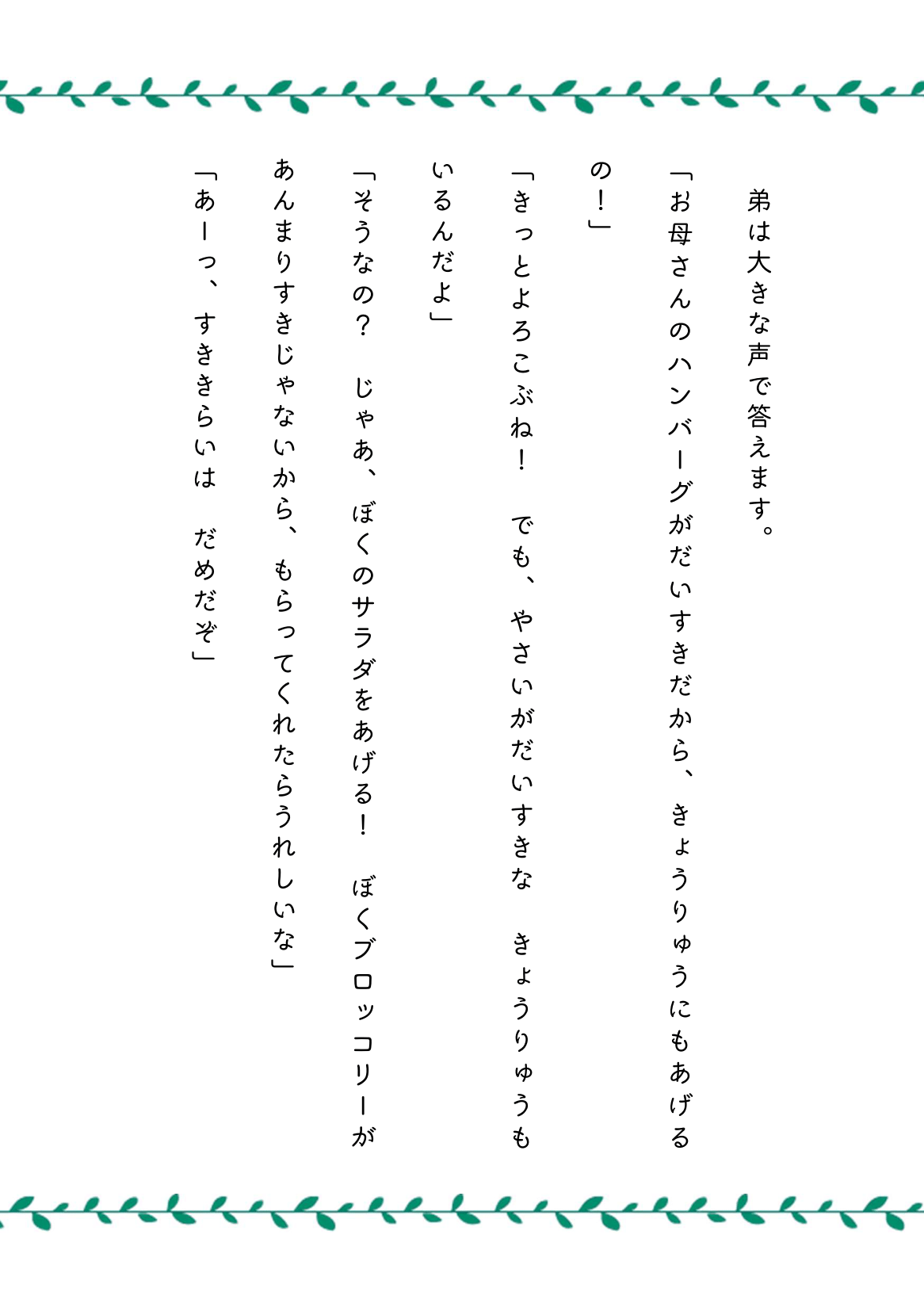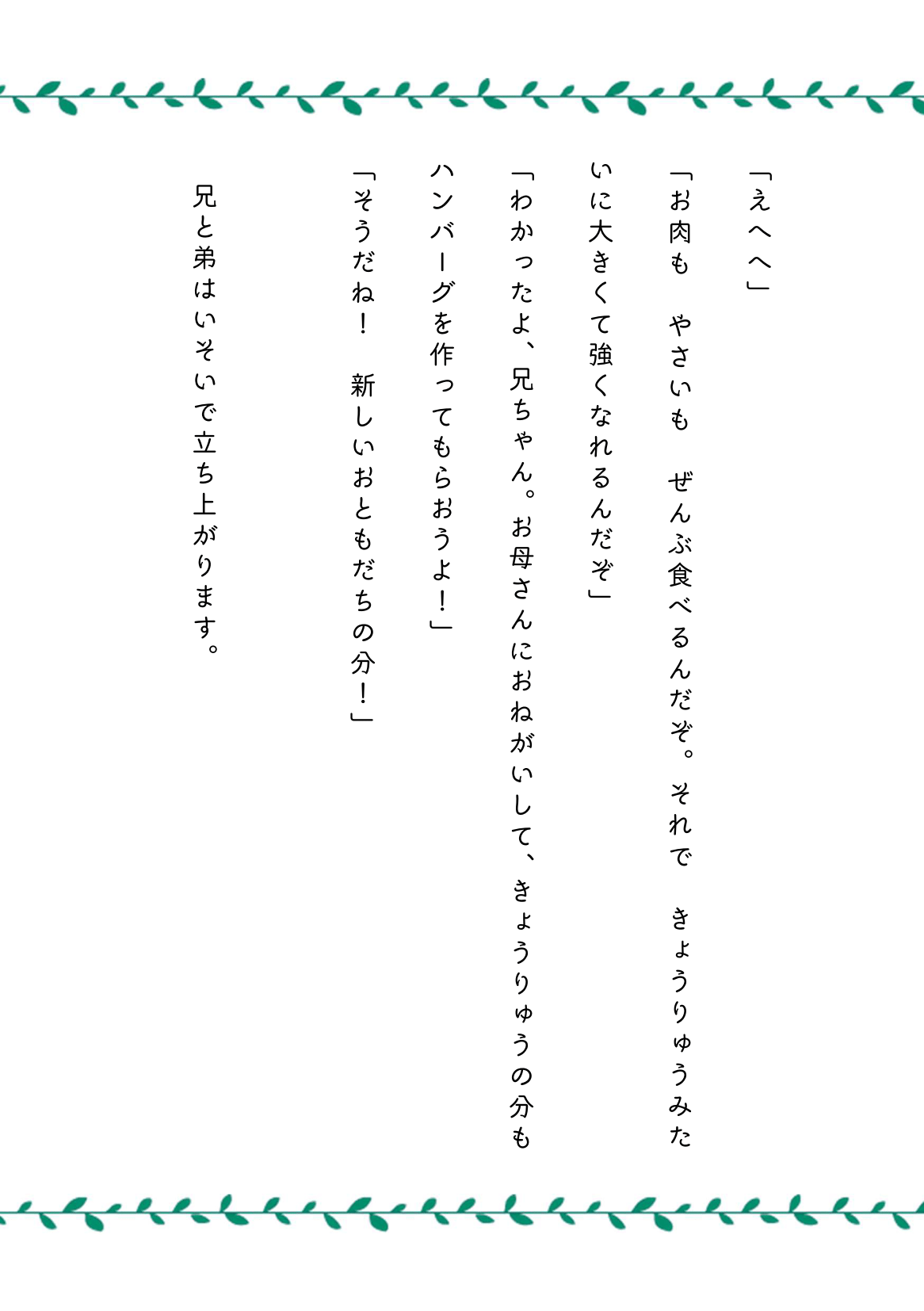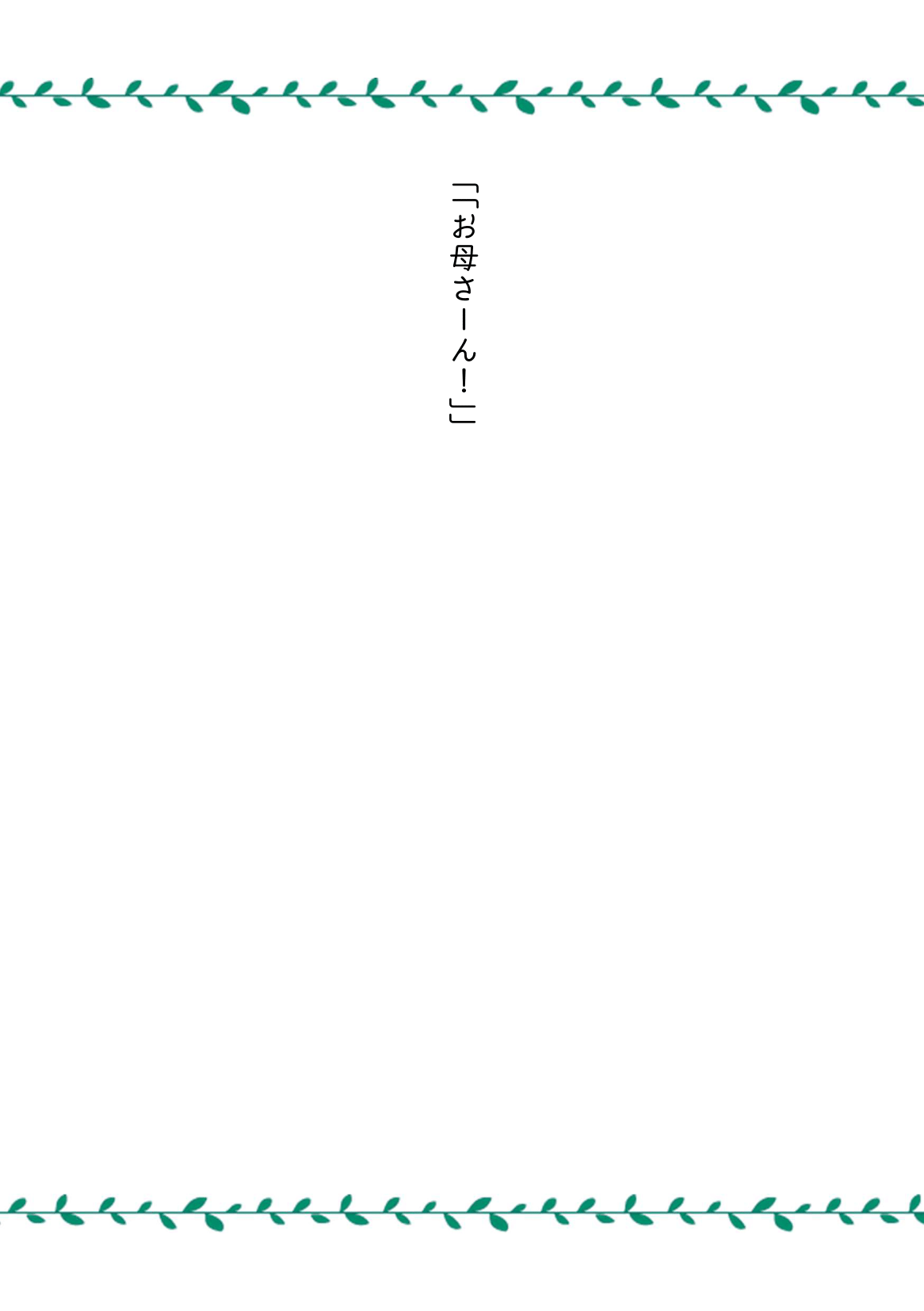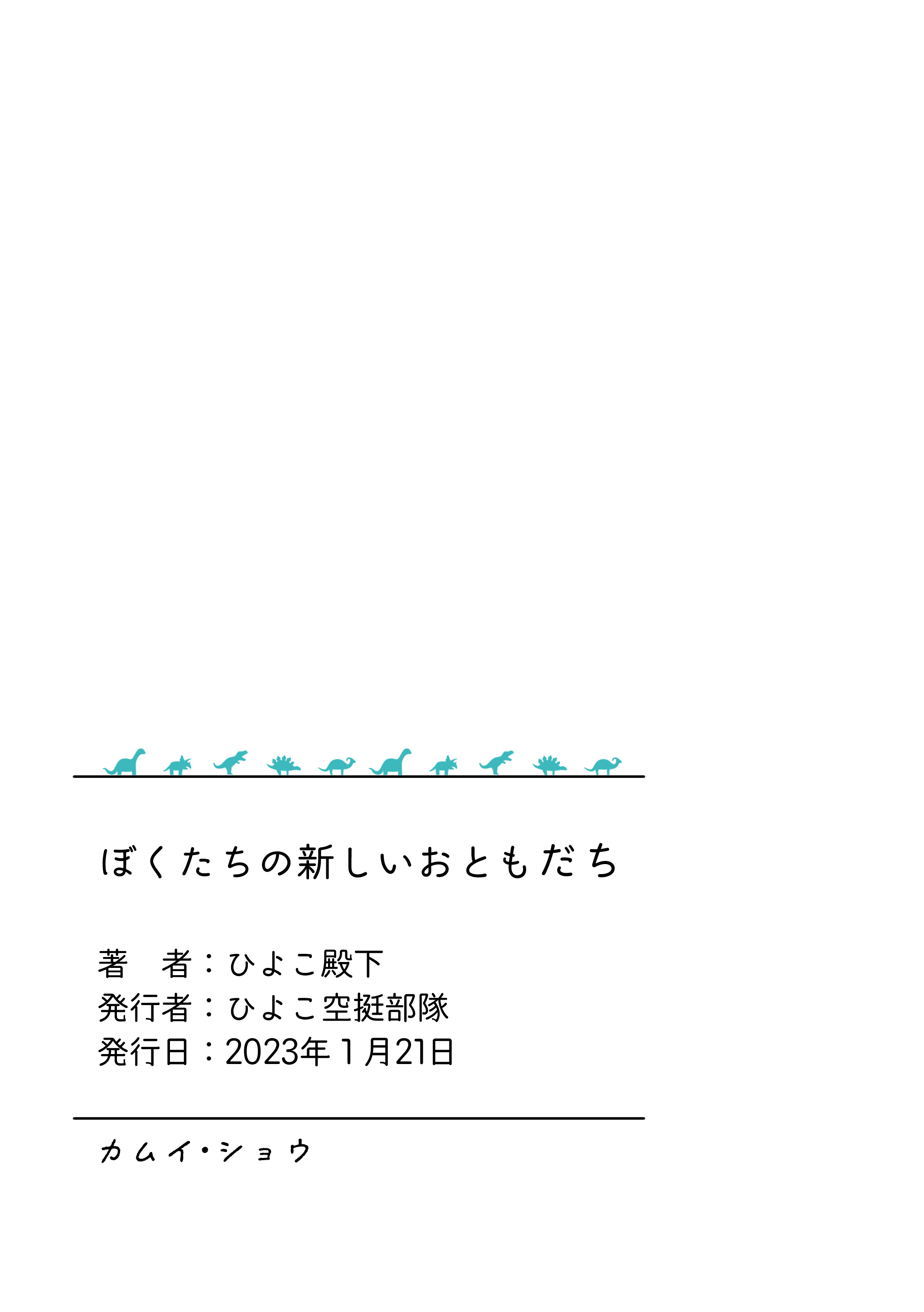2023/1/21開催ゲッターロボアークwebオンリー【Get a Destiny2023】で展示・PDF配布したお話。『恐竜の日』の存在を知った拓馬と獏がカムイにサプライズおめでとうをするお話です。約9,000文字。
・『恐竜の日』は4/17です。
・カムイの誕生日はいつなのか、という話が出ますが、研究施設をめぐるゴタゴタでデータは行方不明、カムイ自身は正確な誕生日を知らない設定です。
・首長竜や翼竜などの爬虫類もここでは「恐竜」に含めています。
・本編の後にちょっとしたおまけがあります。【おまけ】も見てください!
◆◆◆
あーあ、と拓馬が残念そうな声をあげた。
「一月ももう二十一日じゃねえか。結局、正月らしいモン何にもなかったな」
「敵襲ならあったけどな」
獏が苦笑する。
「そんなお年玉、いらねえよ。……なあ、カムイ」
「何だ」
「研究所って、本当に何にもイベントないのか?」
「イベント?」
怪訝そうに、だが手を休めずにカムイが訊き返す。
「だからよ、正月とか盆とかクリスマスとか」
「ない」
即答だった。
「誰かや何かの記念日や祝いごと——誕生日会とかは?」
「必要あるのか」
「せっかく人が集まってるんだから、もう少しこう、ワーッと」
両手を上げる。
「……それで?」
カムイはつれない。
「だからよ、みんなの距離が縮まるようなこと、したっていいだろ」
視線を奪えず中途半端になったポーズを解きながら拓馬が零した。
「こんな時勢にか」
「こんなときだから、もっと楽しいことやみんなですることがあったっていいと思うんだよな。お前、誕生日っていつだよ」
「わからない」
拓馬の表情が固くなる。
「生まれた年はわかる。月もおそらくそうだろうという見当はついている。だが、正確な日にちまではわからない」
「……そうか。悪かった」
「謝る必要はない」
カムイは段ボールの中身をざっと確認し「廃棄」のシールを貼る。そして次の段ボールを開ける。
「事実だし、特に問題があるわけじゃない」
「……」
拓馬の目はカムイの横顔に注がれたままだった。そんなふたりの様子を獏はじっと見つめる。
「拓馬」
カムイの静かな声があがる。
「趣旨は理解するが、今現在『ない』のだから、それが研究所の答えなのだろう」
「…………そんなモンかねえ」
拓馬、と今度は諭すような響きが加わる。
「いいからさっさと片付けるぞ。まだやることはあるんだ」
「わかってるよ。……しっかし、やってもやってもキリがねえな。ここ最近、模擬戦闘のほかは片付けしかしてねえぞ」
「けど、敵が来て被害が出るよりはマシだ」
ぼやきに獏が反応した。
「そりゃそうだけどよ。全滅させられねえんだから、スッキリはしねえよな。な、獏」
「何だ?」
「俺らが倉庫の片付けをしなくてよくなる未来って見えねえのか」
獏は「んん」と唸りながら、目蓋を閉じる。だがすぐに、
「だめだ、全然感じない」
と、大きな目をぱっちりと開いた。
「そこのふたり。いい加減、真面目にやれ」
「やってるだろ」
「その口を閉じれば、もっと効率がよくなる」
「へいへい、わかったよ」
拓馬が方向転換し、二歩進む。さらに進もうと足を出した瞬間、「気をつけろ」とカムイがぼそりと言った。
「え——おわっ⁉︎」
一段低くなっている床にバランスを崩し、前につんのめる。
「っとっと——おい」
「何だ」
「どうせならもっと早く言えよ」
「周囲に気を配っていればわかっただろう? 教えてやっただけ、ありがたいと思え」
「何だと」
「本当のことだろ。さて」
カムイが歩き出す。
「え、もしかしてもう終わったのか」
「ああ」
確かにカムイの背後の棚は空っぽになっていた。
「早くねえか」
「別に。手を動かしていれば終わる。俺は向こうを片づけてくる」
「向こう?」
カムイが指差す。
「あの扉の向こうに、もう少しスペースがある」
「まだあんのかよ……って、お前、さっきから詳しいな」
「お前たちよりは研究所の暮らしは長いからな。……それだけだ」
「ふーん」
拓馬が見回す。
「ここ、暗くて静かで、何だかワケのわかんねえモンがいっぱいあって、秘密基地みてえだよな」
だがカムイはつきあわず、無言で次の場所へ向かった。
「拓馬、俺はあっちをやる」
獏が反対側の奥を示す。
「おう、わかった。じゃあ、俺も本気出すか」
三手に分かれ、しばらく黙々と仕事をこなした。
大きく伸びをして、次の作業に取りかかろうとしたときだった。獏が向こう側から手招きをしていた。
「どうした」
拓馬がすぐに駆けつける。
「あれ、取ってくれないか? 俺、手が入っていかねえや」
「どこだよ」
「ほら、あそこ」
壁と書架の隙間に本が一冊落ちていた。スチール製のフレームに阻まれて容易には取り出せない。書架自体は備え付けで動かせなかった。
「ちょっと待ってろ」
左右どちらから攻めるべきかしばし考え、拓馬が這いつくばる。
「——いよっと」
限界まで左腕を伸ばし、やっとのことで指先で本を取り上げた。
「ほらよ」
「おう、ありがとうな」
「いいって」
作業着の埃を払い、ひょいと覗き込んで——その動きが止まった。
「……」
獏も同じで、本を覆う埃を吹き飛ばしたあとはただ表紙を見つめていた。
「……これって」
子供向けの本とひと目でわかる。
ふたりは顔を見合わせ、再び表紙に視線を落とす。この研究所には似つかわしくない。
獏は無言で表紙をめくる。もう一ページ。文字をゆっくりと追いながら、また一ページ。
そうして最後のページへ。
「————」
ふたりはもう一度、顔を見合わせた。
† † †
カムイの唇からは文句も落ちなかった。
正しくは、落ちる暇がなかった。
「本は冷めねえけど、こっちは冷めちまうんだよ」
謎かけのような言葉を吐き、拓馬が笑う——顔面全部で。あまりにも無垢な子供のようで、カムイの頭の中からは一瞬、自分の役目も、ここがどこかも消えてしまう。
「ほら」
右の手首を掴まれ、はっとする。
「——何を」
「だから、最初に言っただろ。食堂に集合だ」
確かにそう言った。部屋に入るなりだったから、カムイは任務かと訊いた。だが違うと返ってきたのだった。
「理由を言え」
「内緒だ」
「なぜ」
「神さんの許可はもらってある」
途端にカムイがおとなしくなる。拓馬がひゅう、と口笛を吹いた。
「神さんの名前は効果抜群だな」
そうして、また笑った。
「……」
「な、その本置いてよ」
サッと文庫本を取り上げる。
「ん、七十五ページだな」
本を閉じ、机に置く。
「七十五ページ。よし、覚えたぞ」
手首を引いて催促する。カムイはまだどうしたものかと迷っていた。
「カムイ」
「……わかった、行こう」
ひと息つき、立ち上がる。
「行かなければ、お前がうるさい。どのみち、午前の読書時間はおしまいということだな」
「あー、自由時間を取っちまうのは、悪い。けどどうしても、今なんだ」
「別に腹を立てているわけじゃない。それより」
「何だ」
「いつまで掴んでいる」
右手を上げる。一緒に拓馬の左手も動く。
「あ、悪い」
ぱっと拓馬が手を離す。
「行くと言ったら行くさ。それより、急がないと冷めるんだろう?」
拓馬が「あ!」と大きな声をあげる。
「そうだった! じゃあ早く行こうぜ!」
入ってきたときと同じように靴音が騒がしく鳴った。
立ち止まった拓馬につられて、カムイも足を止める。
「ちょっと俺、トイレ」
両手を顔の前で合わせてから拓馬が背後を指差した。
「先に行っててくれよ」
「わかった。……ちゃんと手は洗えよ」
「んなっ⁉︎ 言われなくてもちゃんと洗うって!」
カムイがじっと見ていると、拓馬は「洗うって!」「いいから早く行けよ!」と叫びながらトイレに消えた。
「本当に、騒がしい」
小さく呟いて食堂に向かう。いつもそうだ。けれども、なぜだか嫌な気にはならなかった。
近づくにつれ、様子が違うことに気づく。人の気配はするのに、声がしない。
「……?」
出入り口はカーテンで仕切られ、中がうかがえなくなっていた。まだ拓馬は来ない。
「……」
先に、と言われたのだから仕方がない。カーテンに手を掛けまさに開けようとした瞬間、
「せーの」
小さく聞こえた。
「え」
視界が開けるといくつもの笑顔が飛び込んできた。
「おめでとうー!」
「おめでとう!」
声が重なり、パン! と破裂音がしてカラフルな紙紐が宙を流れていく。
「な——」
すると、背後からもうひとつ破裂音がした。カムイの頭にクラッカーの中身がふわりと乗る。
ゆっくり振り向くと、拓馬がにんまりとして立っていた。
「……トイレは済んだのか」
「おう、あれはちょっとした嘘だ。許せ」
にっ、と笑う。
「それより、ほら入った入った!」
カムイの背中をポン、と押す。訳もわからず促されるまま食堂に入り、改めて拓馬を見る。
「いったい、どういうことだ」
「へへ、こういうことだよ」
拓馬が出入り口の上を指差す。カムイの目がその先を辿る。
「今日って四月十七日だろ」
壁には『祝・恐竜の日』と大胆な筆文字で書かれた横断幕が掲げられていた。カラフルな紙で作られた花がその周囲を飾っている。
「……!」
「カムイ、こっちこっち」
人垣から獏が出てくる。口を開け戸惑うカムイを中央のテーブルへ導く。そこにはずらりと銀色のドームカバーが並んでいた。
「じゃーん!」
真ん中の、一際大きなドームカバーが開けられる。まるでホールケーキのように存在感のある大きなハンバーグが現れた。
「これは……」
デミグラスソースがかかったハンバーグには、恐竜のイラストが書かれた爪楊枝の旗が何本も立っている。
「これは俺が描いた。こっちは拓馬」
可愛らしいトリケラトプスとティラノサウルスがいた。
「これは伊賀利さん」
やたらとリアルで図鑑にでも載ってそうなステゴサウルスだった。カムイが目を向けると伊賀利は照れくさそうに頭をかいた。
「それで、こっちはD2部隊のみんなが」
水島隊員がにっかり笑ってピースサインをする。その後ろに並ぶ面々も得意げな表情だった。
「これはドクター」
にこやかな笑みは検査をするときと変わらない。
カムイは一本ずつ、小さな旗を眺める。アロサウルス、ヴェロキラプトル、アンキロサウルス、イグアノドン、プテラノドン、プレシオサウルス——。
「お前、あんまり騒がしいのは得意じゃねえかもしんねえけど」
少し遠慮がちに拓馬が言う。
「せっかくチームを組む仲間なんだからよ、何か一緒にできればとずっと思ってたんだ」
「……ああ」
「恐竜の日って、要するに人間がハチュウ人類の存在に気づくきっかけになった日ってことだろ」
「結果的にそうなるのだろう」
「なら、ハチュウ人類の血が混じってるお前を祝ったっていいだろ」
カムイの目が大きくなる。
「俺のオヤジの頃とは違うし、お前は仲間だ。だから今日はお前と、お前のご先祖さんの記念日ってことでよ」
「……」
カムイは拓馬を見つめる。それから獏を。カムイをまっすぐに見てくれているみんなを。
「神さんはすぐオッケーしてくれたぞ」
「神さんが?」
意外だった。
「今日も少し遅れるけど来るって言ってくれた。それと、さすがに全員持ち場を離れるワケにはいかないからな。今いない所員は交代制で、あとで来る」
「……そうか」
みんなが楽しめるように考えられていた。
改めて特大のハンバーグを眺める。艶々として、ふっくらとして、とても美味しそうに見える。添えられている野菜の彩りも鮮やかで、カムイの目には美しく映った。
「こっちも見てみろよ」
獏の目配せを合図に次々とドームカバーが開けられる。グリーンピース入りのケチャップライス、スパゲティやグラタン、ピザに唐揚げ、ウインナー、それからお好み焼きにサンドイッチに炊き込みご飯のおにぎり——。飲み物もアルコール以外なら揃っているようだった。
「まだまだあるし、デザートはアイスとプリン、それにケーキもあるんだぜ」
「…………」
研究所の食事情は激務への対価なのか、豊かだった。日替わりメニューもあるし、和洋中と食べられる。だから個々の料理自体は珍しくなかった。けれども大皿に盛られてずらりと並んでいるのは壮観で、さらにはみんなで囲んでいることで特別なご馳走なのだと感じられた。
料理だけではない。食堂の飾りつけも、みんなへの声掛けも。
——全部、自分のために。
こんなふうに祝われたことはなかった。
胸の中がきゅっと押しつぶされるように苦しくなった。けれども不快な痛みではない。むしろ、心地いい。その奥に小さな熱を感じる。やがてその熱はカムイの中にじわじわと広がった。
すう、と息を吸い、ぴっと背筋を伸ばす。そしてゆっくりと息を吐き出し、カムイは周囲の人々と視線を合わせていく。
「ありがとうございます」
噛みしめるように言い、最後に深々と頭を下げた。
「おしっ、じゃあ食おうぜ!」
乾杯と拍手のあとで拓馬がご機嫌な声をあげた。張り切ってハンバーグを切り分け、カムイに差し出す。
「まずは主役からだ」
促され、ひと口食べる。
「……うまい」
「そりゃよかった。さあ、みんなも食べようぜ!」
わあ、と歓声があがる。拓馬も獏も素早く後追いし、「ん!」と表情を明るくさせた。
拓馬がふた口目を頬張る。
「——うめえ!」
「拓馬、このナポリタンもうまいぞ」
「どれどれ。……おっ、本当だ!」
「この魚肉ソーセージがいいな」
カムイは嬉しそうに食べるふたりを見やる。
「それにしても、よく『恐竜の日』なんてわかったな」
「ああ、それな」
パイロットふたりは視線を交わし、笑う。
「俺ら、あるモノを見つけてな。それで知ったんだ」
「あるモノ?」
「ちょっと待ってろ」
皿を置き、拓馬が離れる。
「……?」
壁際のテーブルから紙の平袋を持ってすぐに戻ってきた。
「これ」
カムイは首を傾げながら受け取る。封はされていない。
「見てみろよ」
「本……?」
言われるままに中身を取り出し、その目が見開かれた。
「————」
五秒ほど固まったのち、無言で紙袋だけを拓馬に戻す。そうしてさらに表紙をじいっと見つめた。
ひっくり返して裏表紙をめくる。奥付の小さな文字の下に、さらに控えめな大きさで「カムイ・ショウ」と書かれていた。
「どこで、これを」
「年明けに倉庫の掃除しただろ? あのとき」
「あそこは今まで何度も探した。それでも見つからなかっ——あ」
慌てて口をつぐむが、今度は拓馬と獏の目が大きくなった。
「そんなにお気に入りだったのか」
「いや、その」
珍しくカムイが口ごもり、ふたりから視線を外す。どことなく照れくさそうな、バツの悪そうな表情が浮かんだ。
拓馬と獏はちらと顔を見合わせ、安心したように口元をほころばせた。
「探してたんなら、よかった。見つけたのは獏だ」
「いったいどこに」
「壁際の書架だ」
「書架」
カムイが怪訝な顔つきになる。
「……この本は、いつも下から二段目のファイルの隙間に隠していた。けれどもいつからか、探しても探しても見つからなくなった」
「奥に入れようとした拍子にか、ファイルがぎゅうぎゅうに押し込まれたせいか、裏側に落ちちまったみたいでよ。一番下の棚を空っぽにしたら、壁との隙間に挟まってるのが見えた」
「……そうか。道理で」
「本当に秘密基地だったんだな」
拓馬に小さく頷いてみせる。
電気をつけてもなお薄暗かった。倉庫といっても廃品置き場同然で、普段から人気はない。その閉じられた空間は、幼いカムイにとって本当にひとりになれる場所だった。毎日とはいかないが、わずかな自由時間をよくそこで過ごした。
暗さと静けさが好きだった。壁の隅にお気に入りのクッションを敷き、少しの時間を過ごす。思うままに空想をし、落書きをし、本を読んだ。
やがてその場所を気に入るあまり、自分のものを置いておきたくなった。いつ来てもいいように。それから、誰に示すわけでもなかったが、ここは自分の居場所なのだと印をつけたくて。
だから一番気に入っていた本がないと気づいたときは自分の心の一部が失われてしまったようで、哀しかった。それから、本をくれた人と、本に申し訳なく思った。
そっと表紙を撫でる。
傷みと多少の汚れはあったが、置かれた環境と年月の割には綺麗だった。光による焼けもほとんどなく、記憶にある淡い色の表紙はそのままだった。眩しそうにカムイが目を細める。
捨てられたのだと思っていた。それが何年も経て、戻ってきた。
カムイの眼差しは柔らかかった。
「お前、もっとそうしてろよ」
「何?」
唐突な拓馬の言葉に顔を上げる。
「普段のクールな感じもいいけどよ、今みたいなカムイもいいと思うぜ」
「それは、どういう……?」
「ま、もちろん、無理に笑う必要なんかねえけどよ」
それで、たった今自分が笑っていたのだと気づく。
「笑うことで引き寄せられるものもあるし、お前の笑った顔を見たいって人もたくさんいると思うぜ」
拓馬が白い歯を見せた。
「…………」
カムイは本に視線を落とし、それから横断幕を仰ぎ見た。力強い筆跡で、ところどころはみ出している。自由でありながら信念を感じさせる勢いがあった。
「あの横断幕な」
獏が隣に並ぶ。
「あれ、敷島博士が書いてくれたんだぜ。すげえカッコイイよな」
「……そうだったのか」
とても彼らしい。
「拓馬、獏」
「ん?」
ふたりの顔を交互に見つめる。
「……ありがとう」
カムイは静かに告げた。
食堂は賑やかだった。あちこちから笑い声が聞こえてくる。今だけは平和な時間だった。
「そういえば、敷島博士はどこに?」
まだ横断幕の礼を伝えていない。カムイが辺りを見回す。
「あれっ? 最初のほうはいたろ?」
拓馬もきょろきょろと視線をさまよわせる。
「見えねえな。なあ! 敷島博士知らねえか?」
呼び掛けると「花火の準備をしてくると言ってました」とどこからか返ってきた。
「花火? ってまさか……」
三人は顔を見合わせる。
「おい、絶対普通の花火じゃねえよな」
拓馬が眉をひそめる。
「ああ、絶対に」
獏の眉毛も緊張感にきゅっと上がる。
「……研究所を吹き飛ばさなければいいが」
「おい、シャレにならないこと言うなよ!」
カムイの言葉に拓馬が突っ込んだときだった。
「————っ‼︎」
警報が鳴り響いた。瞬時に全員の目の色が変わり、空気がひりつく。間髪入れず、誰もが自分の役割を果たすために走り出した。
「空気の読めねえ奴はお引き取り願おうか」
拓馬が不敵に笑い、手にしたポテトフライを口に放り込む。
「腹ごなしにちょうどいい」
ハート型にくり抜いた人参のソテーをぱくりとやり、獏も笑う。
「なら、さっさと片付けてもう一度乾杯といこうか」
カムイの提案に、ふたりが「おう!」と答えた。
食堂を出て最初の通路を曲がると敷島博士と行き合った。何やらボタンがついた装置を握っている。
「お前たち! これから花火を上げるぞ! 特製の昼花火じゃ!」
ぴょん、と飛び跳ねてアピールする。
「せっかくだからアークの中で見るぜ! 敵にも見せつけてやろうぜ!」
「博士! ありがとうございます!」
「特等席で花火見物だ!」
パイロット三人が次々に駆け抜けていく。
「ドカンと一発どころじゃないぞ! 三万発のお祝いじゃあ〜っ‼︎」
心底楽しそうな笑い声が通路に響いた。
† † †
モニタ画面を見つめる隼人の目は普段よりも穏やかだった。誰の視線もない自室だからか、それとも——。
傍らには、コーヒーとラップに包まれたサンドイッチがある。迎撃と後始末、襲撃パターンの分析などで時間を食い、結局祝いの席には顔を出せなかった。あとからカムイが申し訳なさそうに、それでも嬉しそうに礼を言いながら、この軽食を差し入れに持ってきたのだった。
セキュリティカメラの録画映像を眺める。食堂内の誰もが楽しそうにしていた。音声はなくとも笑いさざめく様がわかる。
ある時点で映像を止め、戻す。もう一度再生し、止めたところで画像を保存する。拡大して同じ作業を。
「……」
このカムイの表情には見覚えがある。
彼が研究所に来たばかりの頃だった。見た目のいとけなさ、可愛らしさのせいだろう、カムイへ、と女性所員たちが数冊の児童書を持ってきた。カムイは知能が高く、またその出自ゆえにずいぶんと大人びた考えと佇まいを身につけていた。だからそれらの本は読み物としてはだいぶ物足りないだろうと思っていた。
しかし三日ほどのち、本はどうだったかと訊ねたら、「とても気に入りました」と細い声とはにかんだ笑顔が返ってきたのだった。
あのときと同じささやかな笑顔。見えるものはわずかであっても、自然に湧いてきたものだとわかる。
隼人は画像をフォルダに入れ、パスワードをかける。それをほかのデータ——前回の通信以降にこちらで得た敵の情報と分析結果、カムイの最新の生体データ——に紛れ込ませる。もちろん、容易には見つけられないように。
彼がこの仕掛けに気づかなかったら仕方がない。けれども見つけてくれるはずだという妙な確信があった。今まで送ったものも、きっと見つけてくれている。そして隼人の意を汲んでくれるものと期待していた。
「……これでいいだろう」
再度チェックをする。漏れはない。隼人はコーヒーをひと口飲むと、サンドイッチに手を伸ばした。パンは少し乾燥していたが、十分に美味しかった。
彼宛てにデータを送信する。
「……」
送信中を示すバーが完了に近づいていく。隼人はじっと見守る。
そして願う。
この世界で誰よりも、カムイの笑顔を祈っている女に届きますようにと。
〈了〉
おまけ